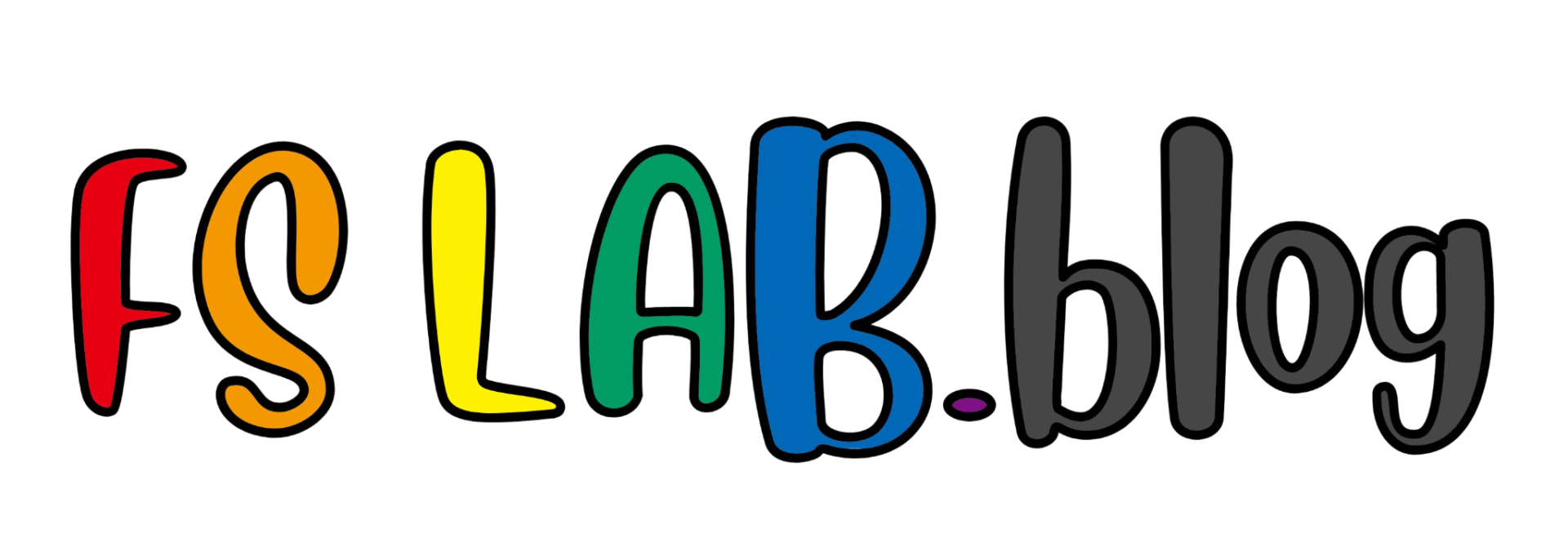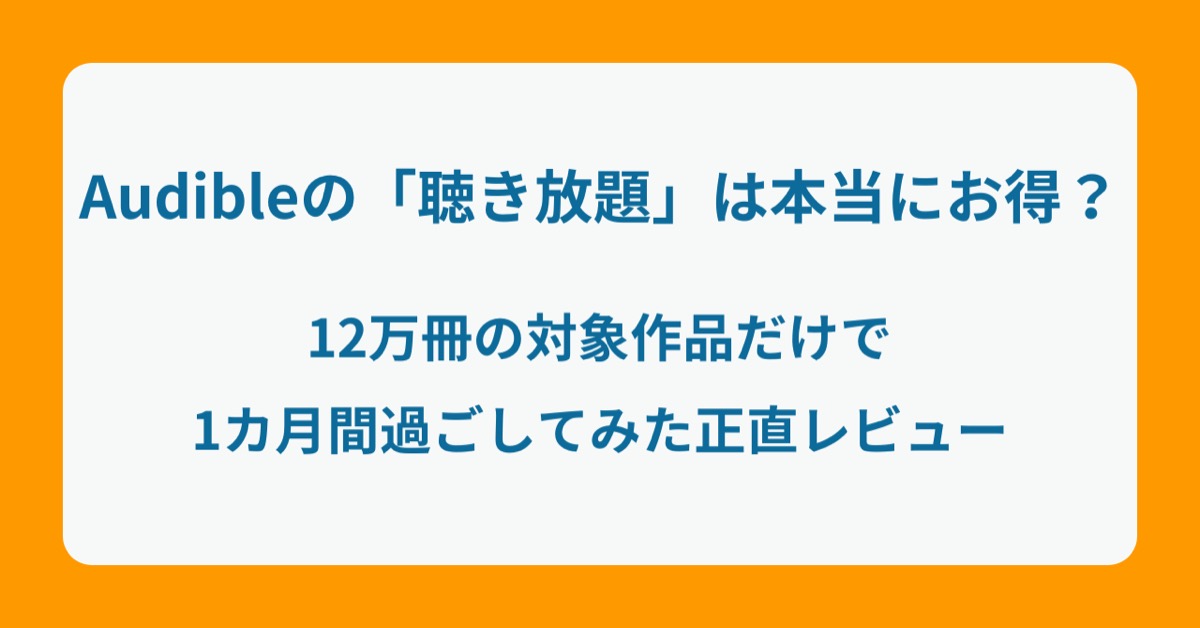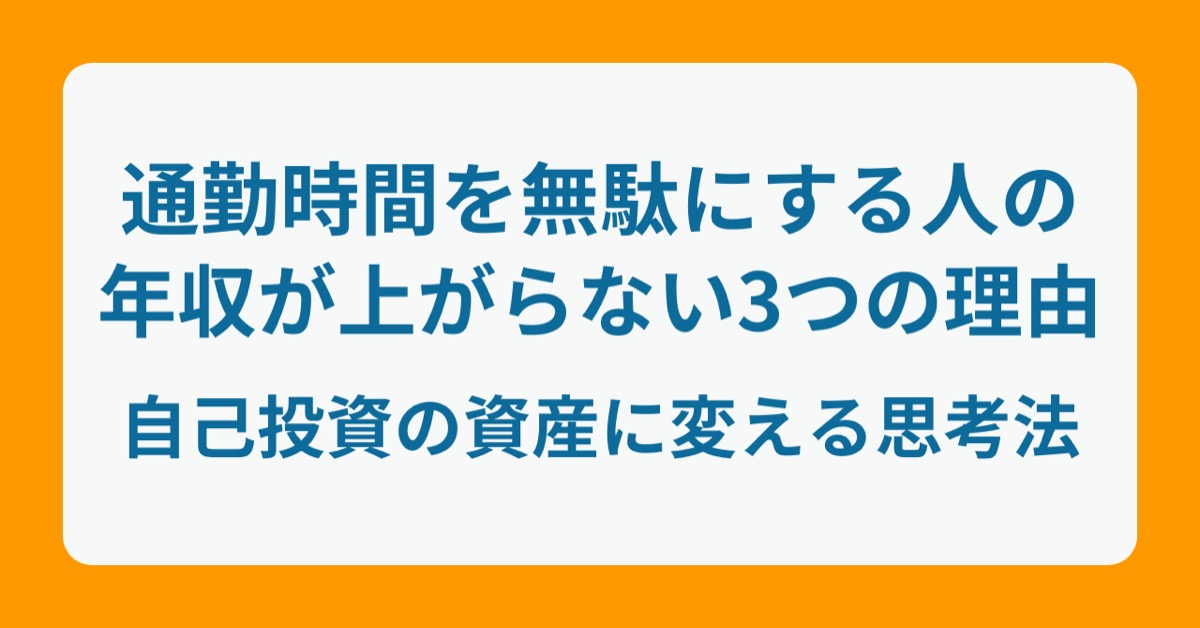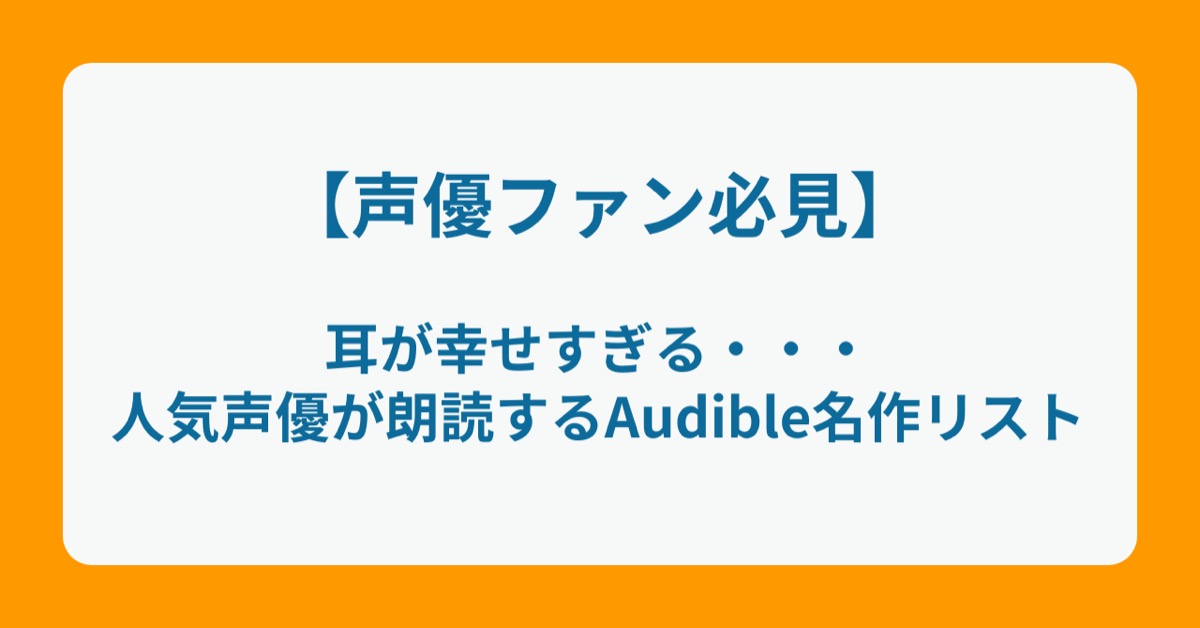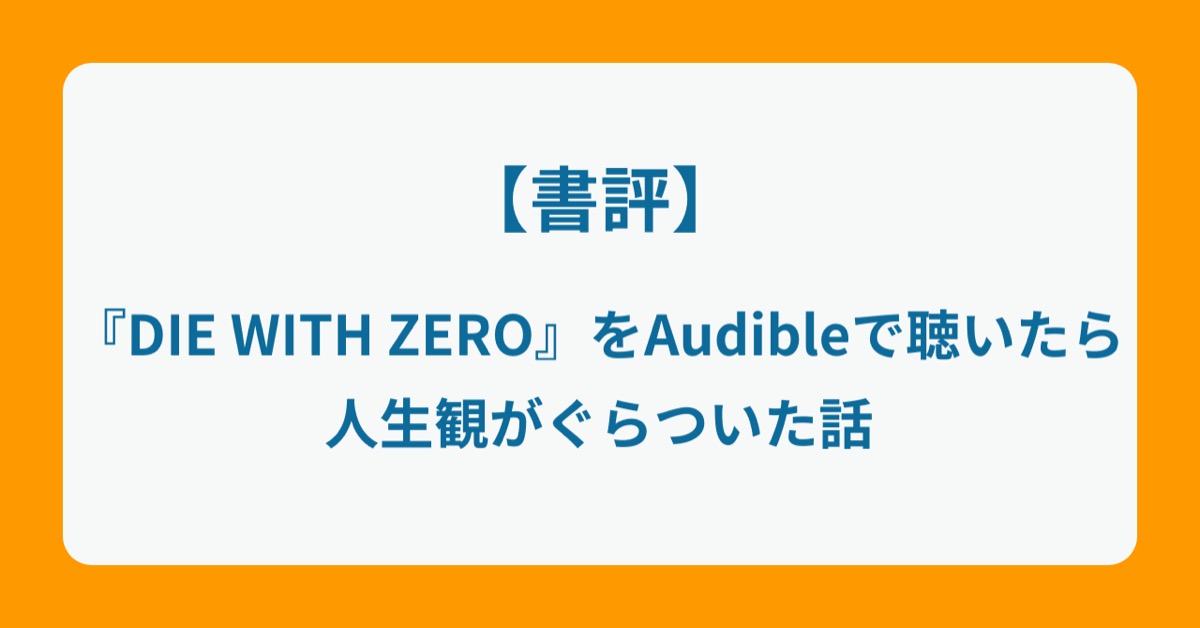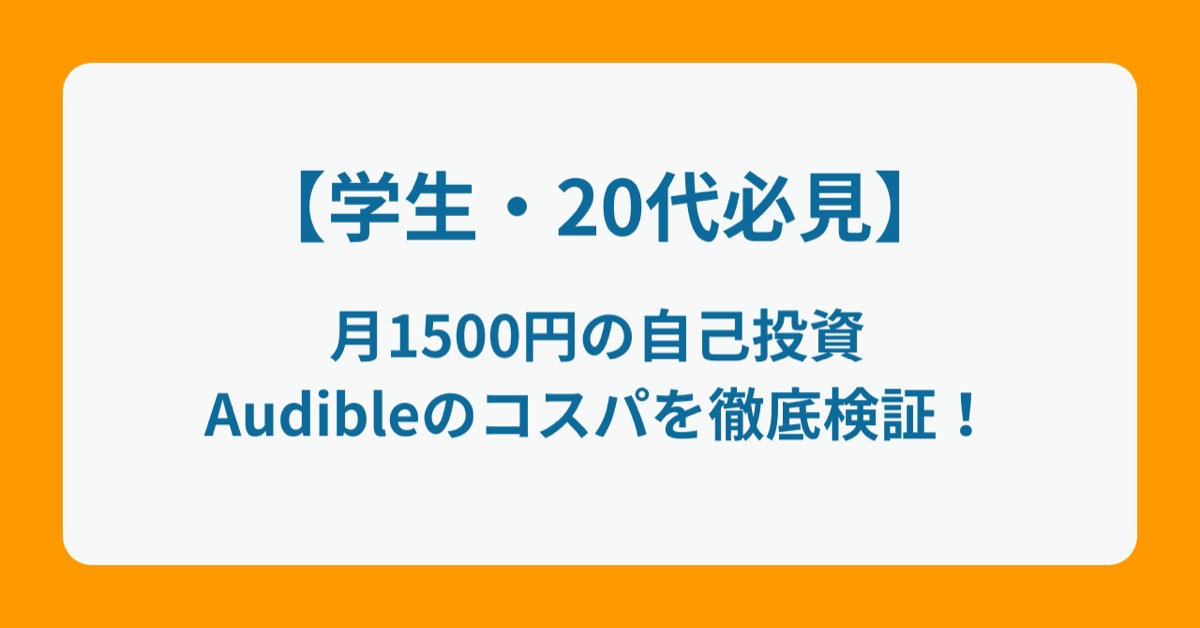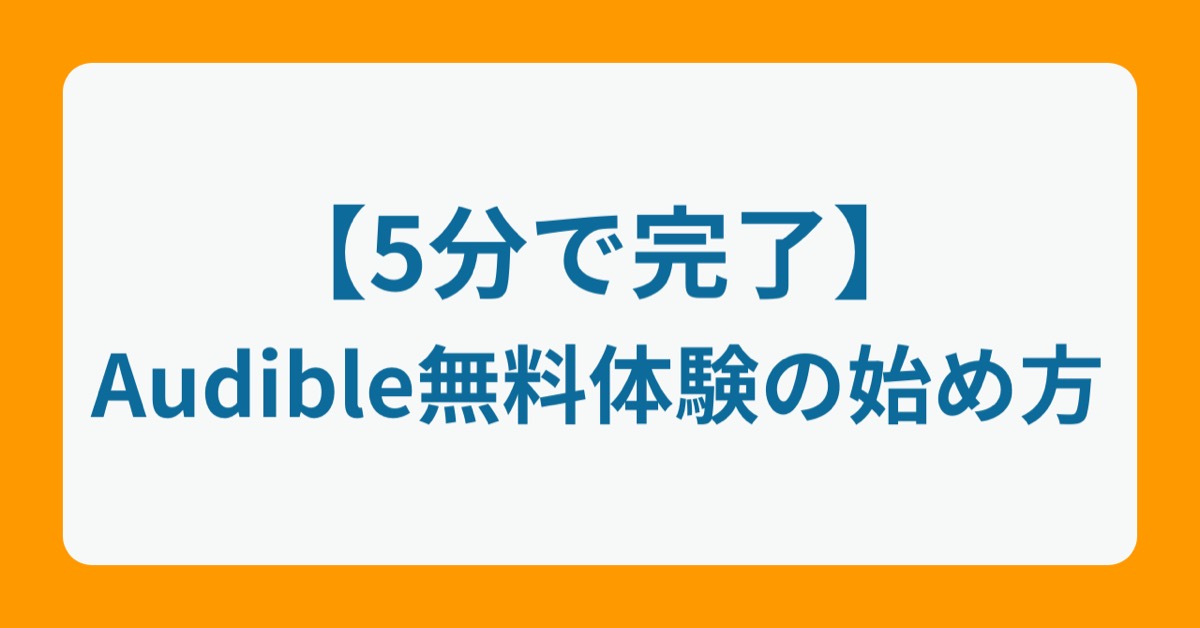Audibleは読書じゃない? 「音の体験」として評価すべき3つの理由
Audibleって「読書」なの? という疑問に元・読書嫌いがマジレスしてみる
こんにちは!
最近、友人からこんなことを聞かれました。「Audibleってよく聞くけど、あれって『読書』になるの? 結局、読んではいないよね・・・」と。
なるほど、この気持ちすごくよく分かります。
僕も昔は、本は目で読むものという固定観念がありましたから。
今回は、この「Audibleは読書なのか?」という、多くの人が心のどこかでモヤモヤしているであろうテーマについて、僕なりの考えを書いてみたいと思います。
この記事を読み終えるころには、あなたのそのモヤモヤが、新しいワクワクに変わっているかもしれません。
そんなこんなで本題です。
「本は目で読むもの」という常識を疑ってみる
まず、多くの人が「Audibleは読書なのか?」と感じてしまう根っこには、「読書とは、目で活字を追う行為である」という、あまりにも強力な常識がありますよね。
学校の国語の授業も、図書館も、本屋さんも、すべてはこの常識の上に成り立っています。だから、耳で聴くスタイルに、どこか「本流じゃない感」を抱いてしまうのは、ある意味で当然のことなんです。
でも、少しだけ立ち止まって考えてみませんか?
そもそも、「読書」の目的って何でしょうか。
文字を目で追うこと自体が目的でしょうか? 恐らく違いますよね。
本に書かれている情報や物語を知ること、著者の考えに触れること、それによって自分の知識が増えたり、感動したり、人生が豊かになったりすること。
きっと、こちらのほうが本質的な目的のはずです。
だとしたら、その情報をインプットする手段が「目」でなければならないというルールは、一体誰が決めたものなんでしょうか。
「ロボット読み上げ」との決定的な違い
「とはいえ、スマホの読み上げ機能ならタダだし、それで十分じゃない?」
はい、次に出てくるのはこの意見です。これもまた、すごくよく分かります。コストをかけずに同じことができるなら、それに越したことはないですから。
ただ、僕個人の意見を言わせてもらうと、Audibleとスマホの読み上げ機能のTTS(Text-to-Speech)は、まったくの別物です。
これをものすごくざっくり言うと、「カーナビの音声案内」と「大好きなラジオDJのおしゃべり」くらいの違いがあります。
カーナビの音声は、情報を正確に伝えることだけが目的です。感情も抑揚もありません。「500メートル先、右方向です」という声に、心を動かされる人はいないですよね。
一方、ラジオDJのおしゃべりはどうでしょう。同じ情報を伝えていても、そこには絶妙な「間」や、楽しそうな笑い声、リスナーを惹きつける語り口があります。だから、私たちは何時間でも聴いていられるし、内容もスッと頭に入ってきます。
Audibleの体験は、完全に後者なんです。
・Audibleの価値は、本の内容を音声で聞ける「機能」ではありません。
・プロのナレーターや声優が作り出す「音の体験」そのものにあります。
僕が「音の体験」と評価する3つの理由
では、その「音の体験」って具体的に何がすごいの?という話をしますね。
1. ナレーターは「声の俳優」である
Audibleのナレーターのかたがたは、単に文字を読んでいるわけではありません。彼らは「声の俳優」です。
例えば、ビジネス書に出てくる著者の熱いメッセージ。
これをロボット音声で聞いても、ただの文字列が耳を通過するだけです。
でも、プロのナレーターが読むと、そこに著者の「情熱」や「悔しさ」といった感情が乗っかります。まるで、著者が隣で直接語りかけてくれているような、そんな感覚になるんです。
不思議なもので、感情と結びついた情報って、すごく記憶に残りやすいんですよね。
2. それは「音響作品」である
特に、Audibleが自社で制作しているコンテンツの中には、BGMや効果音が巧みに使われているものがあります。
ミステリー小説で、犯人が背後に迫ってくるシーンで微かな足音が聞こえてきたり。
歴史小説で、合戦のシーンで遠くから鬨の声が聞こえてきたり。
これはもう、「読書」というより「映画を耳で体験している」感覚に近いです。
この圧倒的な没入感は、他のサービスではなかなか味わえない、Audibleならではの大きな魅力だと僕は思います。
3. 「聴く」って、意外と疲れない
仕事で一日中パソコンの画面と向き合っていると、もうヘトヘトですよね。
そんな状態で、家に帰ってから本を開くのって、結構な精神力がいります。
「聴く読書」のいいところは、この「頑張るぞ!」という感じが、ほとんどいらないところです。
ソファに寝転がって、目を閉じたまま聴ける。
お皿洗いをしながら、お風呂に入りながらでも聴ける。
この「ゆるさ」が、習慣として続けやすい大きなポイントなんです。
頑張ってインプットするというより、好きな音楽を聴く感覚で自然と知識が自分の中にたまっていく。そんなイメージです。
とはいえ、活字が恋しくなるときもある
ここまでAudibleの魅力を語ってきましたが、もちろん僕も紙の本や電子書籍が嫌いになったわけではありません。
図やグラフが多い専門書を読むとき。
美しい写真がメインの雑誌を眺めるとき。
何度もページを行き来しながら、じっくり考えたい哲学書を読むとき。
こういうときは、やっぱり「目で見る」メディアのほうが向いているなと感じます。
大切なのは、どっちが優れているかという二者択一で考えることではないのかもしれません。
料理で、炒め物にはフライパンを、煮物には鍋を使うように、インプットしたい情報や、そのときの自分のコンディションに合わせて、最適なツールを使い分ける。
そんな感覚が、一番しっくりくるんじゃないかなと僕は思っています。
というわけで:大事なのは「なんと呼ぶか」より「豊かになるか」
さて、いろいろと語ってきましたが、最初の問いに戻りましょう。
「Audibleは読書なのか?」
僕の今の結論は、「どっちでもいいんじゃないかな?」です。
なんだか無責任に聞こえたら、ごめんなさい。
でも、これが僕の正直な気持ちです。
それが「読書」という立派な名前で呼ばれようと、そうでなかろうと、その体験があなたの人生を少しでも豊かにしてくれるのなら、それはもうめちゃくちゃ価値のあることだと思うんです。
「これは読書なのか?」という罪悪感のようなもので、新しい世界の扉を開けるのをやめてしまうのは、あまりにもったいない。
もし、あなたがかつての僕のように「読書は苦手だけど、何か学びたい、物語に触れたい」と思っているなら、ぜひ一度、騙されたと思って「音の体験」に身を委ねてみてください。
大事なのは、その行為を「なんと呼ぶか」ではなく、その行為によって「あなたの日常が、きのうより少しでも豊かになるか」どうか。
ただ、それだけなんだと思います。
では、また!